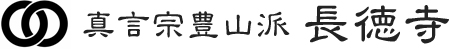長徳寺についてAbout
長徳寺の縁起
当山は真言宗豊山派(総本山は奈良県桜井市・長谷寺)に属し、挙一山遍照院と号します。
創建された年代は不祥ですが、境内にある石塔の銘から行慈阿闍梨が建久年間(1190~1199)に中興開基したと推定されます。本尊は不動明王で錦戸親観師によって昭和38年に彫られたものです。
『新編武蔵風土記稿』(文政11年)に「新義真言宗、多摩郡中野村宝仙寺末、挙一山遍照院と号す。大日を本尊とす。鐘楼、寛保三年鋳造の鐘をかく。」とあります。
昭和20年4月13日に堂宇はことごとく戦災をうけましたが、同38年に本堂・客殿書院・庫裡、そして同55年に山門が再建され、再興いたしました。
境内にはかつて大日堂があり、運慶作と伝えられる一丈六尺の大日如来像が本尊として安置されていたので、「子育て大日尊」、「乳授けの大日さま」と呼ばれ親しまれ、乳の出ない母親が米を供えて21日間住職に祈願してもらい、寺の井戸の水で炊いた御飯を食べると乳が出ると信じられていました。
当山に安置されている阿弥陀如来立像は、もとは平泉・中尊寺蔵で平安時代後期頃の製作と推定されます。平成5年2月26日に板橋区指定有形文化財となり、木一材による彫出で口元に笑みをたたえた穏やかな面相などの表現は、当時の様式を探るうえでも貴重な仏像といえます。
その他、弘法大師像・興教大師像・六道絵図等が安置され、境内には大日如来・釈迦如来・観音菩薩・地蔵菩薩・弁財天などの石仏が残っています。
また民俗資料として貴重な力石が五個ほどあります。表面に重さを表す何貫目と刻まれた卵形のもので、大日さまの縁日には遠方からも人が集まり、力石をかつぎ大日堂のまわりを何周も回り力自慢に興じたといわれます。 主な年間行事としては、本尊不動明王の縁日に因んで毎年五月二十八日に施餓鬼会を厳修しています。

阿弥陀如来立像
(板橋区指定有形文化財)

本尊不動明王像
長徳寺の概要


| 寺号 | 真言宗豊山派 長徳寺 アクセス |
|---|---|
| 所在地 | 〒174-0061 東京都板橋区大原町40-7 |
| 電話/FAX | TEL:03-3960-0957 FAX:03-3960-4895 |
| 山号 院号 | 挙一山 遍照院 |
| 本尊 | 不動明王 |
| 宗派 | 真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは) 奈良県桜井市初瀬にある、総本山長谷寺の山号の豊山をいただき真言宗豊山派と称します。 長谷寺は十一面観音の霊場として広く信仰を集め、また牡丹の名所としても有名です。 東京音羽の護国寺は大本山です。現在末寺三千ヶ寺、檀信徒約二百万人を数えています。 |
| 総本山 | 長谷寺 奈良県桜井市初瀬 |
| 祖師 | 宗祖 弘法大師(空海) 四国讃岐に生まれ、都の大学に進みましたが、出家して新しい仏教を求めて唐に渡られ、密教の秘奥を極め、帰国後、高野山に金剛峯寺を建立し、真言宗を開かれました。
中興祖 興教大師(覚鑁)高野山での修行後、根来山に移り、瞑想法に力を注がれました。また、密厳浄土への往生など、わかりやすい教えを説かれ、中興の祖といわれます。
派祖 専誉僧正戦国時代、根来山より長谷寺に入山し、復興されました。その後に徳川家康に寵遇され、真言宗豊山派の基礎を作られ、学僧の誉れ高く、派祖と仰がれています。 |
| 開宗 | 真言宗は、平安時代初期に弘法大師によって、中国からもたらされ、わが国で開宗されました。 |
| 教え | 大日如来を中心とした曼荼羅思想などです。 |
| 礼所 | 豊島八十八ヶ所霊場 第14番 |
| 読誦するお経 | 般若理趣経・光明真言などです。 |
| ご宝号 | 南無大師遍照金剛・南無興教大師・南無尊誉僧正 |
| 文化財 | 板橋区文化財・阿弥陀如来立像 |